


今野様
30代前半
大学研究員
2回
基礎・短答・論文パック、論文添削ゼミ

医学部の大学院にいた頃、知財の授業を受ける機会があり「特許というものがあるんだな」と興味を覚えたのが始まりです。
はい。ずっと理系ですので、選択論文は免除になりました。
経歴としては学部時代は理学部の物理学科で、大学院は医学部に進みました。
専攻に大きなこだわりはありませんでしたが、新しい技術が好きな性格で、「弁理士なら新しいものに色々触れられる」と考えたのが弁理士試験を受験する動機になりました。
誰もいなかったですね。SNSも試験後に他の人の反応を知りたくて見ることはありましたが、勉強仲間を探すような使い方はしませんでした。
地方在住のため通学という選択肢はありませんし、「家で好きな時に勉強できる予備校があれば」と思って探し、資格スクエアにたどり着きました。
カリキュラムや教材に対しての料金の安さも大きな決め手でした。

↑合格実績豊富なカリキュラムを
リーズナブルな価格で受けられるのが
基礎・短答・論文パックの特長
2022年の11月から学習を開始し、23年は短答で合格を逃してしまいましたが、24年に短答・論文・口述に受かりました。
1年目の学習ですが、学習開始後、年内は基礎講座をひたすら視聴しました。もちろん内容的に分からない部分はたくさんありましたが、とりあえず1周することに重きを置きました。
その後は青本講座を経て、短答対策に取り組みました。
短答まで時間が限られていましたし、1周目は初めて尽くしでどうしてもかなりの時間がかかるので、やはりこうやらざるを得なかったかなと思います。
もし時間的に余裕があるならば、論文対策を多少やってから短答対策に移ります。
まずは論文式試験でもよく聞かれるような部分を重点的に埋めていくことで、短答対策はスムーズになると思いますね。
一年目の反省を踏まえ、二年目の短答学習は少しやり方を変えました。
「特許の大問を2問解いたら別の分野の大問を解く」というように、数問単位で科目を変えるスタイルにしたんです。
以前は特許なら特許で、分野もひとつずつ順番に全部やっていましたが、数問ずつ変化をつけて回していくのが自分にはとても合っていてすごく良かったと感じています。
一つの分野だけずっとやっていると、頭がそちらに固まってきてしまいますが、色々なものに少しずつ取り組むことで知識も整ってきます。
過去問を周回する時に、正解・不正解はもちろんですが、解きながら「この問題の根拠は何条の何項」と頭に思い浮かべてから解説を見るんです。そして覚え切れていない条文を洗い出し定着させていきました。
そして3~4周目になったら、今度は「何条の何項」だけでなく、条文全体を頭の中に思い浮かべてみて、出てこなかったらもう一度条文を引く。5~6周目には、条文の趣旨が頭の中に思い浮かばないところがあれば青本を引く、という感じです。
正答がどうこうというより、思い出すきっかけとして過去問を使っていたと思います。これ以外も、準用や周辺条文など、問題から派生させて知識を呼び起こすことで記憶を盤石にしていきました。
今年は何があっても合格するつもりだったので、どんな問題が出ても、もし不測の事態があったとしても受かる状態にしておこうと思いました。
その甲斐あって、模試では1位を取れました。
また、24年の短答式試験は自分の中で「結構間違えたな」と思っていたのですが、結果的には50点で突破することができました。
実は一年目の短答式試験を落とした後、しばらく勉強をやめていたんです。そして2023年9月頃にまた再開し、ここで初めて論文学習に取り掛かりました。
この頃は短答の学習はせず、論文添削ゼミ(秋期)と論文書き方講座を受けて、自分なりに書き方を模索していました。
まず、一時中断していた勉強を再開する良いきっかけになりました。
論文添削ゼミに取り組むときは、条文や青本の振り返りも同時に進めました。
条文自体は一年目の短答式試験の時点でかなり頭に入っていたのですが、論文ゼミの際に関連する条文を改めて引くことで、知識が解凍されていきました。また青本に関しても関連する部分を引いて趣旨も少しずつ覚えていきました。
そうした作業を積み重ねながら、時間をかけて答案を書き上げていった形です。
短答には手を付けず論文添削ゼミ中心で学習した頃は、正直なところあまり安定して勉強していたわけではありません。
提出期限の前日に集中して仕上げるなど、ある意味ではゼミの締め切りがペースメーカーとなり牽引してくれたため、とてもありがたかったです。
2024年の年明けに二年目の短答対策にシフトし、3月以降は大問を一日120問は解くようにしていました。
上でお話ししたようなやり方で短答過去問を解いていましたが、この頃やった短答学習が後々論文にも非常に活かされたと感じます。
短答式試験の直後とその翌日に解き方講座と実践講座を観て、講座の視聴はここで完了しました。短答対策で知識のインプットはほぼ完了していたので、ひたすら構成を取っていました。
まず講座の1周目は、林先生の板書と照らし合わせてしっかり構成を取りました。2周目以降は構成を取ってノートと一致するか確認して、違うところがあれば「何が違うのか」を考えるという流れでやっていました。
ただその後に模試を受けてみると、たとえ構成が取れていても、そこから実際に全文書きをする時にするする書けるという状態ではなくて、「ちょっとギャップがあるな」と感じたんです。
そこで、講座で構成を取った紙を見て、そこからレジュメの模範解答を導き出せるようになるまで、頭の中で繰り返しトレーニングしました。最終的には解き方講座と実践講座を10周して、「もう何が出ても大丈夫」という状態に持っていきました。
短答式試験が終わって最初に論文の模試を受けた時、あまりにも疲れてしまって「これを毎日やってると死んじゃうな」と思ったんです。
「とりあえず最速で構成を書けるようになって、全文書きも頭の中でイメージできるようにしないと手首が持たないな」と。
3周目以降は、全文書きをシミュレートするだけでなく、さらに構成も頭の中でやるようになりました。
チェックポイントまでいったら、実際の構成と照らし合わせて合っているかどうかを確認して、、という形で回し、極力書く時間を減らすようにしていました。
それはありました。例えば特許は所要時間2時間のうち40分は構成に使いました。残り1時間20分で全文書くわけですが、間に合うかどうかの瀬戸際です。書きたいことはたくさんあっても物理的に間に合わなくなるので調整に苦労しました。
ただそこは数をこなすうちに戦法が見えてきて、科目によって書き方を変えるなど工夫しました。具体的には、特許はどんどん当てはめ重視で書いていって、時間があれば規範を書き加えた感じです。意匠商標は逆に、最初に規範を立てて丁寧に書きましたね。
終わった後はできたことよりも書き漏れやミスの方が頭に浮かんで、大丈夫と思いつつも少し不安な気持ちがありました。
ただ今になって思うと、「どこが書けなかった」と気づけるくらいの人の方が、受かってるんじゃないかな?と思いますね。
私は2日目だったので、X(旧Twitter)で1日目の人達の「すごく変わった問題が出た」という反応を見ました。そこで変にヤマをはらずに、条文を一通り全て見返して知識のメンテナンスをして本番に臨みました。
実際の試験では、最初の特許は初受験ということで雰囲気も分からず緊張しましたが、雑談に入ってくれたので「もう大丈夫だ」と安心しました。
一方で、商標は結構厳しい試験官でしたね。とはいえ全て時間内に終わったので、比較的穏やかな気持ちで会場を後にしました。
資格スクエアの講座、特に論文講座に関しては、「解き方講座」と「実践講座」がかなり完成度の高い講座だと思います。
問題のタイプごとに毎回同じ手順で解いていくという解法を身につけることが、本番でも活きてくるし、何より迷わなくて済むというのが一番の良いところだと思います。
林先生が、「この内容が身についていれば模試でも60点を下回ることはなくなる」とおっしゃっていましたが、実際に模試や本番で分からない問題には出会いませんでした。
正確に言うと本番では初見の問題に出会うのですが、身につけた解法で書いていけるので、間違いなく合格点には届く、という実感が得られました。
可能であれば、短答の勉強に専念する前にこの気持ちを味わいたかったですね。

↑論文式試験合格に求められる解法を
ステップ別に身につけられる、林講師の「論文対策講座」
それから、今でも記憶に残ってる菊池先生の言葉があります。誰かが「細かい部分が覚えられない」という話をした時に、菊池先生は「プロになったら覚えるのが当たり前だ」とおっしゃったんです。
実務家として30年以上のキャリアのあるからこそ出てくる言葉だなと、その姿勢が深く刺さっています。

↑時に厳しくも、本質をつく菊池講師と
受講生と同じ目線に立つ林講師
2名の異なる切り口が、合格を引き寄せます
現在実務修習を受けていますが、その後は弁理士に転職したいと考えています。
その後は、明細書を作ることはもちろん訴訟にも関わっていきたいです。「知財に関わることは一通りできるようになりたいな」という気持ちでいます。
勉強をしたくてもできない日や、できない時期はどうしても出てきます。毎日続けられるならそれに越したことないですが、なかなかそうもいきません。
大切なのは「いかに復帰するか」だと思います。
勉強しない期間が延びていくとだんだんやる気もなくなってきますが、そこで何とか奮起して勉強に戻ることです。今振り返ってみると、それが一番重要なポイントだったと思いますね。
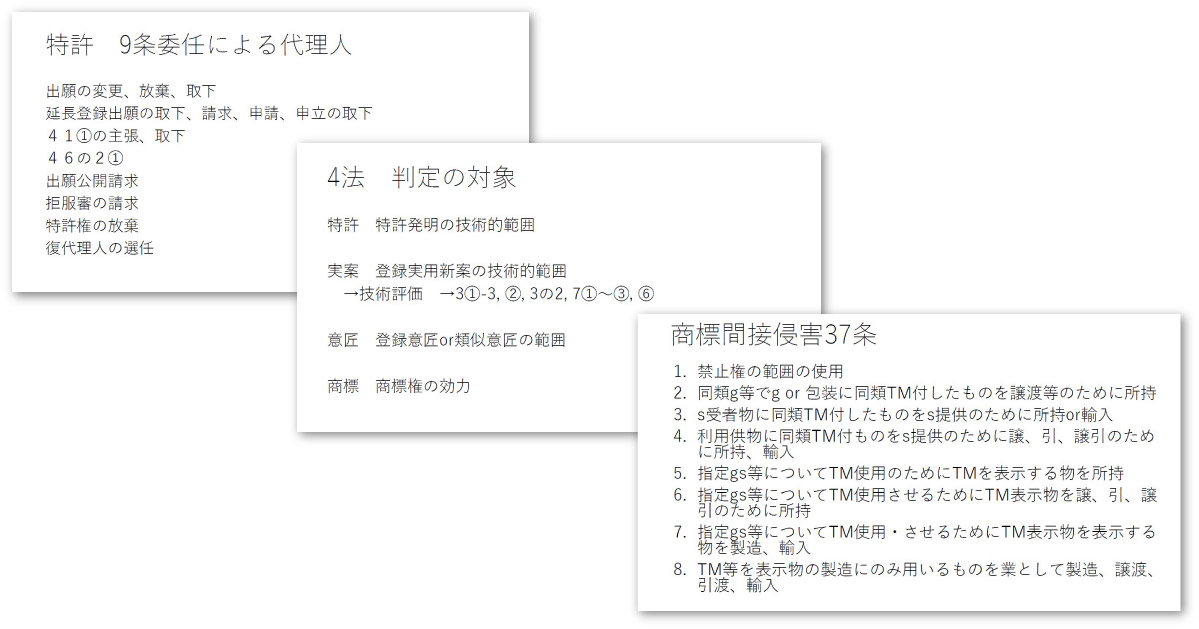
↑短答対策用の資料として
自分が覚えられていない内容をまとめて一元化

↑論文の構成のまとめなどを書いたノート
寝る前と起床時に毎日頭に思い浮かべていたそう

↑論文実践講座の要件資料の部分に
自ら趣旨を書きこみ、情報を一元化